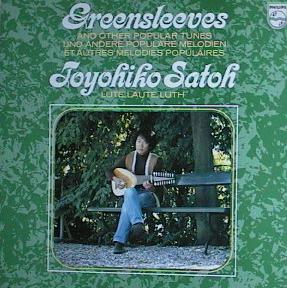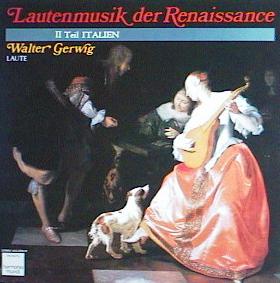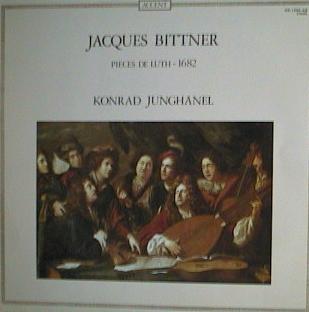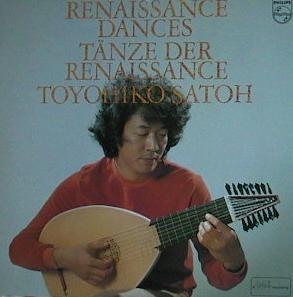リュートについて (リュートを知るには)
リュート・古楽の団体
リュートが描かれた絵画
リュート愛好者のHP
レコード・CD
演奏会
リュート・古楽の団体
下記のサイトを訪れてみて下さい。
僕がなんだかんだと述べるより、
サイトからリンクを辿った方がいいでしょう。
リュートに関するHPがたくさんあります。
なおLINKはしていません。サーチエンジンで検索して下さい。
★★★
NPO
日本ルネサンス音楽普及協会 |
芸術・文化の振興及び
保健・医療・福祉の増進を図る活動を目的として
設立されたNPO法人です |
| 日本リュート協会 |
リュートとその音楽の普及、振興
国内、
国外の情報交換と親睦 を目的に設立された団体です |
★
先頭に戻る
リュートが描かれた絵画
リュートが絵の中に描かれた作品がたくさんあります。
楽器をどういう風に構えるのか、どんな弾き方をするのか、
絵からだいたいの事がわかります。
リュート奏者 高本一郎氏のホームページの中の
LUTE GALLAERYというコーナーにリュート絵画を集めたコーナーがあります。
リンクはしていませんが、サーチエンジンで「リュート絵画」と検索してみて下さい。
★★★
★
先頭に戻る
リュート愛好者のHP
個人が開設しているホムペを訪れるのも良いでしょう。
ここに紹介する、みっちいさんと琵琶乃院さんのサイトは必ず覗いています。
LINLしています。バナーかタイトルをクリックして下さい。
★★★

michi house
音楽の部屋
|
北海道でリュート弾く主婦、みっちいさんのサイトです。
みっちいさんの演奏が聴けます(演奏データあり)。すごく素敵です。聴いてみて下さい。
他にリュート以外の「部屋」もあります。 |
★
| Lute Cookies |
九州で活躍されている、琵琶乃院さんのサイトです。
長野でひとり弾いている僕にとって情報源にもなり、刺激を受けてるホームページです。
ブログも公開されています。 |
★

恋のうぐいす
|
クラシック音楽(主にバロック以前)と、古楽器のリュートをテーマとしたくーぷらんさんページです。 |
★
先頭に戻る
レコード・CD
リュートを知るには、CDなどを聴いてみるのもひとつです。
★★★
レコード
僕がリュートに興味を持って以来、聴き続けてるものを紹介します。
「レコード」なので、今入手出来るかわかりません。CDによって再販されているかも知れませんが・・・
★
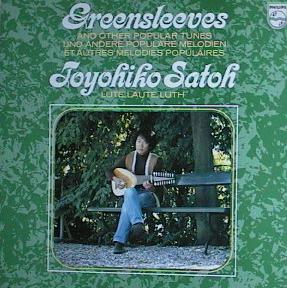 |
グリーンスリーヴス/佐藤豊彦 カッティキング、ダウランド、アテニャン、ノイジドラー、ガルシ・ダ・パルマなど、
イギリス、フランス、ドイツ、イタリアの作品が収められています。
リュート曲によるヨーロッパ訪問といったところでしょうか。
僕がリュートに興味を持ち、一番最初に購入したレコードでした。
B面8曲目の、ガルシの「平気な顔で嘘をつく女」は僕の好きな曲で、
耳コピーで弾いてみましたが、和音が分からず、楽譜を入手できたらと思っています。
フィリップス 25PC-138 \2,500
|
★
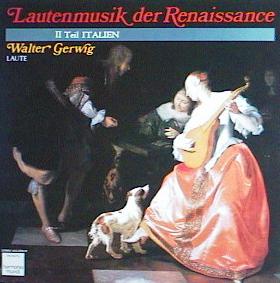 |
ルネサンス・リュートの魅力 第2集イタリア編/ヴァルター・ゲルヴィッヒ ガリレイ、フランチェスコ・ダ・ミラノ、ガルシ・ダ・パルマ、メリ・ダ・レッジォなど、
イタリアの作品が収められています。
この中では、メリの「半音階的カプリッチォ」がお気に入り。半音階の上昇が印象的です。
これも耳コピーしようとしたんですが、ちょっと無理でした(笑)。
このレコードで聴くゲルビィッヒの音色が好きです。彼はバロック・リュートの作品を別の調弦で弾いたとか
批判があったようですが、タブラチュアが残された作品は、勝手には手を加えるような事はなかったそうです。
僕はこのホームページの中で、バッハの作品をルネサンスリュートで弾いてますが、
僕にとっては、歴史的とか忠実な再現とかよりも、いかに楽しむかが重要です。
もちろん正しいリュートの知識を得た上で。
テイチク ULS-3294-H \1,500
|
★
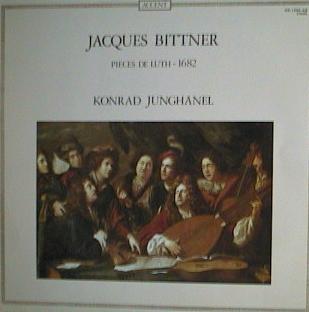 |
ビットネル リュート曲集/コンラート・ユングヘーネル ハ長調、ロ短調、ト短調、嬰ヘ短調の四つの組曲が収められています。
ビットネルという作曲家については、ほとんど知られていない謎の音楽家だぞうです。
曲はどれもフランス風。個人的にフランス風の曲の大げさな装飾音は苦手なんですが、
ここに収められている曲は、むしろそれを排除しようとする素朴さがあります。
日本コロムビア OX-1292-AG
\2,500
|
★
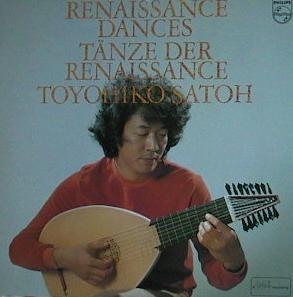 |
ルネサンス舞曲集 トリスターノの嘆き/佐藤豊彦 中世紀末からバロック初期にかけてのヨーロッパ各地の代表的な舞曲を集めています。
「エスタンピー」、「バス・ダンス」、パッサメッツォ」、「パヴァーヌ」、「ガリアード」、「ブランル」など、
14世紀から16世紀まで、舞曲の歴史をたどる構成になってます。
|
★★★
先頭に戻る
演奏会
なんと言っても、生の音を聴くのが一番です。
★★★
先頭に戻る
|